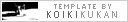2006年05月08日
●ザハ・ハディド in 原美術館
正式名称は「ザハ・ハディドとめぐるドイツ銀行コレクション「舞い降りた桜」」です。原美術館を舞台にして、世界的に評価の高い建築家ザハ・ハディドが構成した空間に沿って、ドイツ銀行のアートコレクションを鑑賞する、はずなのですが。。。私的には美術館5、ザハ3、常設展示1、企画展示1という割合でした。なので「ザハ・ハディド in 原美術館」です。
原美術館は中庭とそれを囲む建物が素晴らしいです。屋上テラスから眺める青い空と蔦で覆われた煙突(?)も好きです。重みのあるスチール建具、距離によって見え方の変わる壁面タイルも趣があります。面白グッズでいっぱいのショップも良いです。時間と手間をかけて醸成された雰囲気が特に良いです。
そして、その中心に出現するザハ・ハディドのインスタレーション。ザハといえば、イメージの奔流の如き、鋭角でパワフルなドローイング。あれが具現化すると、周囲をなぎ倒すようなバイオレンティックな存在と化すのか?と思いきや、実際にはハンカチをそっと置くような繊細で柔らからな存在で、「舞い降りた」というフレーズ通りです。中庭と見事にマッチしています。角度を変えればパワフルな曲面もありますが、その勢いは空へと流しています。原寸で制作したスタイロフォーム原型をそのまま送って組み立てたそうですが、さすがな面構成です。
そのインスタレーションの影が建物内に流れ込み、会場内を誘導する仕掛けみたいですが、床に貼ったシートがペラペラで元の床のデコボコが浮き出てしまい、かなりチープ。イメージに空間が追いつけない感じでした。厚いと扉の開閉に支障が出るし、塗ってしまうと原状回復が大変だしで、仕方のないところでしょうか。そして展示を観るわけですが、これがどうもピンときませんでした。ゲルハルト・リヒター「船遊び」、やなぎみわ「かごめかごめ」、アンドレアス・グルスキー「アトランタ」、オラフ・ニコライ「自然に習って1」等々、気になる作品もあるのですが、全体に素っ気ないというか入り込めないという感じです。現代アートなんだからそんなモンよという気もしますが、「選りすぐり」という部分に分かり易さを期待していました。
そんなわけで、満足度はけっこう高い展示でした。そろそろザハ・ハディドの建築も日本上陸でしょうか。

●表参道ヒルズ
表参道ヒルズは、その前身となる同潤会青山アパートの竣工から約80年を経て建替えられた再開発プロジェクトです。設計は森ビル+安藤忠雄建築研究所、竣工は2006年1月です。計画のポイントは、建物の半分を地下に沈め、建物壁面を上下(商業と居住)で分割することで青山アパートのスカイラインを残し、ケヤキ並木の街路空間を維持していることです。さらに青山アパートの一部を復元する等、「過去の継承」にとても配慮されています。それに加えて、吹抜けに面した6層スロープによる「新しい価値を付加」しています。言葉でいうと簡単ですが、その実現は驚異です。建替計画のあり方として、最高の回答の一つだと思います。
関東大震災後の復興計画として出現し、耐震性、耐火性に配慮され、計画面でも先進性のある同潤会アパートも大半が姿を消しました。30年で過去のイコンと化す現状を見ていると、70-80年持った同潤会は優れた計画だったと思います。
維持された街路空間。この時点で計画は半分成功だと思います。

吹抜に面した6層スロープ。シームレスにつながる立体街路の効果は絶大で、GWのもの凄い人出を、蟻地獄の如く吸い込みます。

スロープの眺め。文字通りの立体街路です。緩やかな勾配が連続するので、自然と足が動きます。車椅子の方が通行されていて、そういえばバリアフリー空間であることを思い出しました。空間のスケールと人出に圧倒されて、そこまで頭が回りませんでした。

復元された青山アパートの一部と、そのスカイラインを連続するガラスのファサード。まだ違和感がありますが、時間の経過と共に馴染んでくるでしょう。

●燕子花図と藤花図
先日「燕子花図と藤花図」展を鑑賞しました。根津美術館は今日から3年半、改築のため休館なので、その見納め展示です。
ガランとした室内に屏風だけを並べる構成は、展覧会というよりも四季の眺めを楽しむお祭りの気分です。「吉野龍田図」の春・秋、尾形光琳「夏草図」の夏、「蹴鞠図」の春を経て、7ヵ月ぶりに尾形光琳「燕子花図」と再会します。季節は夏、水辺と八橋すら省略した構図と、金地に青緑の色彩。大胆な絵だなと思います。せっかく空いた室内なので、真ん中に畳を敷いて座敷から四周を眺める形で鑑賞できれば、なお良かった。狩野宗信「桜下麝香猫図」の春を経て、円山応挙「藤花図」へ。初夏の快晴の日、季節感ピッタリのこの絵が今回の主役だと思います。金地に薄墨の枝が這い、細密で色鮮やかな藤花が垂れる。写実をベースに装飾性を加味した絵は、品良く親しみやすさ抜群です。鶴沢探鯨「草花図」を経て、鈴木其一「夏秋山水図」の夏・秋で一巡です。
一巡したら、真ん中の椅子に座って四周を見回してみます。座敷に立てて眺めたらこんな感じかなと想像しつつ、のんびりと眺めます。四季の屏風に囲まれたその先には、どんな景色を観ていたのだろうか。きっと絵に負けない佳景が広がっていたのだろうな。立地も庭園も申し分ない根津美術館です、新館への期待が高まります。
庭園には杜若。(花菖蒲かも)

そして藤花。しばしのお別れです。

●花鳥-愛でる心、彩る技 <若冲を中心に> 第2期
「花鳥-愛でる心、彩る技 第2期」を鑑賞しました。今回は多彩な鶴の描写に興味がそそられて、会場を何度も回って見比べました。
入口を入ると「群鶴図屏風」が目に入ります。金地にモノトーンの鶴がズラズラと並び、一風変わった雰囲気を醸しています。バーク・コレクションの「大麦図屏風」と似ている?中ほどに行くと狩野探信「松薔薇に鶴・竹梅に鶴図」、円山応挙「双鶴図」が並び、見慣れた「絵画の中の鶴」に出会います。特に後者のクリクリッとした眼の正面顔、気持ち良さそうに目を細める横顔、ペタリと胴に沿う翼、柔らかな足先の描写は絵としての鶴を消化し尽くした感があります。そしてクライマックスが伊藤若冲「動植綵絵」の一つ、「梅花群鶴図」です。黒の点目に、細く伸びる嘴、その中に生える歯、フグの薄造りのような翼。なにより画面左手に顔だけ出してエロ目で笑う(?)表情の豊かさ。とても生々しく、薄皮を剥ぐかのような細密な描画、それでいてとても美しい世界。あれも鶴ならこれも鶴、くらくらします。
絵画の伝統を支えたのは狩野派や応挙なのでしょうが、奥行きを広げたのは若冲なのだろうと思います。広げすぎて明治の人には底なし沼に思えたかもしれませんが、時間を経て現代に至れば、その影響(?)が漫画や劇画に垣間見られて面白いです。
大手門をくぐって見返したところ。日に日に緑が濃くなってきます。